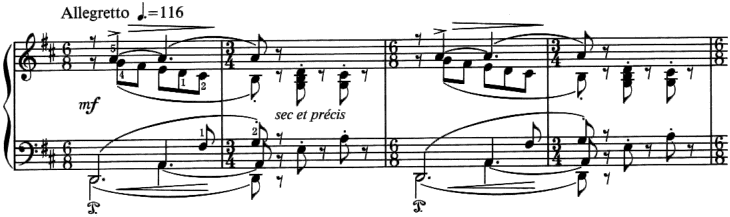
 Home > Gallery > イベリアの風景 >
Home > Gallery > イベリアの風景 >
フェードインする形で、「イベリア」の新たな世界に誘[いざな]う作品。ライブでは巻毎に必ずと言っていいほど拍手が入りますが、できれば静かに終了する前曲「セビリアの聖体祭」から連続して聴きたいところです。この繋がりにすら美しさを感じます。「ロンデーニャ」はアンダルシア民謡の一つの形式。スペイン南部にあるロンダ市あたりで発祥したものと言われています。
「港」より更に明確に、6/8拍子と3/4拍子が1小節ごとに目まぐるしく変わっていきます。左右の手で、クレッシェンドとデクレッシェンドが行き交うところに注目。
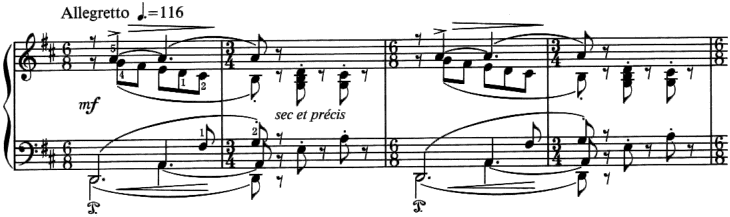
16小節の長い序奏が終わると、狭い中音域で第1主題が現れます(○で囲んだ音符がそれ)。いきなり手の交差にて惑うところ。実は、序奏を上下ひっくり返した転回型です。
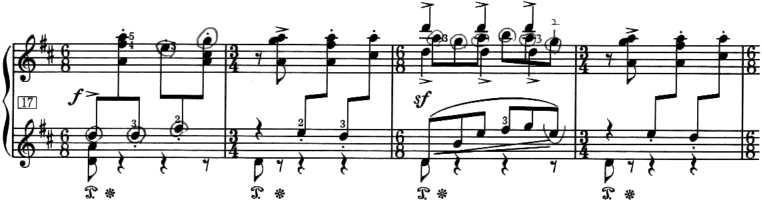
突然ですが運指法のコーナーです(^^)。第1主題の変形が現れるのですが、音が入り組んでいてどこが主旋律なのか分かりません。アクセントさえしっかり出せれば、漠然とクラスター的に弾くのが逆に面白いのでは?ということで、なるべく指の交差がないように、次のような運指にしてみました。
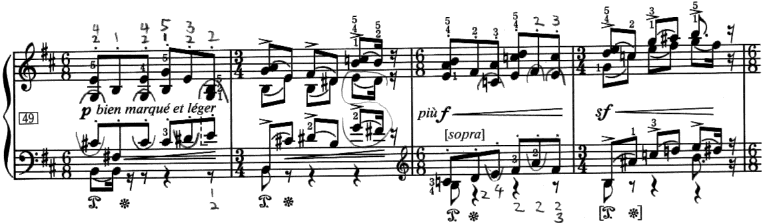
切羽詰まる音型が続いた後、第1主題が晴れやかな形で復帰します。しかし、ここもオクターブによるスタッカート奏法やトリルが非常に難しい。

アレグロで奏でられていた軽やかな舞曲が終了しPoco meno mossoの柔らかな部分に移る。ここでは、左手の伴奏音型に(これまた)挟まる形で第2主題が現れる。ここに現れるトリルはすべて拍と同時に奏すとうまくリズムにはまる。Unwinはそれを怠っている。

Alpuerto版では、トリルが拍と同時に開始することを音符の実長で明記してあります。

「ラ・ベーガ」でも事例を紹介しましたが、Alpuerto版、Gonzalez版では自筆譜の偏重しすぎる嫌いがあります。 初版譜にこそアルベニスの意図が書き込まれていることもあることを意識すべきです。
ロンデーニャでは135小節目、初版譜や春秋社版では以下のようになっています。

しかし、自筆譜では以下のように最初の右手の和音などが存在しません(上譜例では○内および左手の「ミ」)。まさかこの和音が出版社によって勝手に付与されたとは思えません。出版社に自筆譜を提供後、アルベニスが追加させたとしか考えられません。また、ここは小さな場面転換の場所でもあるので、何度弾いてみても、和音があった方がしっくりします。春秋社版では他の版が和音を削っていることを認めつつ和音を残しました。英断だと感じます。

ただし、上下の楽譜で、もう一つ差があります。それは、自筆譜側のスラー記号の大幅な削除です。曲の大半でこの削除が見られます。自筆譜で削除したものを出版時に復活させたのか、あるいは出版社が削除マークを見落としたのか。私自身は、アルベニスが出版の際に上記和音を追加したのならば、出版譜をチェックしていたと考えられます。このスラーの復活もアルベニスの目に入っていたのではないかと推測します。
再現部では次のようなトリッキーな主題の融合が順番で登場します:
それでは順番に見ていきましょう。
左手で第1主題が奏でられている間に、右手で見た目重厚そうな和音が降りてくるところ。右手は序奏の変形と考えられます。したがって、この部分は、序奏と第1主題の融合と考えられます。右手は小さな音量かつ軽いタッチで弾かれます。ロンデーニャに興じる踊り手と、後ろで伴奏したり手拍子をする人たちの動きの対照が、左右の手で表現されているような雰囲気。ロンデーニャ以降に頻発するアルベニスならではの技法です。174、176小節の○をつけた音符は右手の和音の間に挟まれるものですが、左手で強めに弾くことで光彩を放つ効果があります。なぜ手の交差が必要なのか?と疑問に思われたらこのような部分を実際に自分で弾いてみると答えが見えてくるかもしれません。

いよいよ、クライマックスに入ります。第189小節、第1主題がオクターブで奏されると、それに1小節遅れて第2主題が左手に現れ(ここにも手の交差)、掛け合いが始まります。

上の譜例で、最初はイ長調ですが、第193小節目からはニのフリギア調になります。更に進むと、第197小節目の第2拍から全音音階に…協会旋法を介した音色の自在なコントロール。ただただ脱帽するばかりです。

なお、上記第200小節目5つめの和音に誤記があります。それについては次の節で。
大変充実した校訂内容の春秋社版ですが、わずかながらに誤謬が存在します。わずかとはいえ、森安氏の厳しい目と耳を通過し、聴感上不自然には聞こえない間違いであるため、誰かが指摘しない限り発見しづらいものとなっています。
まず、上の譜例にもある第200小節。以下の譜例の一番右にあるように(って見えにくいですが)、5つめの和音は、b-gis-bではなくb-fis-bです。

また、以下の譜例最後の小節。左手3拍目のA音も誤記可能性が大きいです。
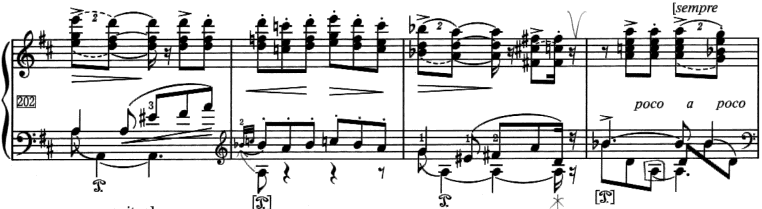
以下に示すとおり、Gonzalez版やAlpuerto版ではG音です。類似箇所としてこの第204-205小節は第223-224小節に対応していると考えられます。第224小節では春秋社版でも左手のベース音がGとなっています。このようにずっとA音で安定させるよりはG音に変えた方が変化が出て面白くなります。
誤謬とは関係ありませんが…第204小節の最後に入っている16分休符の指示は無視できません。明確にここで音を切ることで次の小節へ異なる雰囲気で入ることができるのです。これもアルベニスの作品に頻発する表現指示です。

上記2つの譜例にもあります3小節目冒頭(第203小節)、どのように装飾音を弾くか迷うところで、版によっても解釈が異なります。上記Gonzalez版では右手も使用しています。しかし、自筆譜を見ると演奏方法が明記されています。私もこのアルベニスの弾き方がベストではないかと思います(春秋社版の演奏ノートとも一致しています)。

クライマックスの後、ゆっくりと静けさの中にとけ込んでいくところ。今度は、序奏の音型と第2主題が美しく融合します。この部分は何度弾いてもその心地よさ、懐かしさに浸れてしまいます。

第253小節(以下の譜例の3小節目)、春秋社版ではpppp(p 4つ)ですが、自筆譜を見ると、ppppp(p 5つ)となっております。最弱音を奏でましょう。
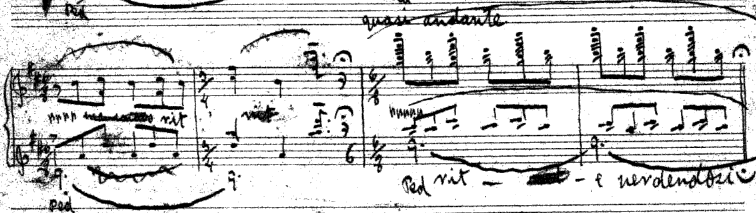
このあとゆったりとした第2主題が2度奏でられた後、曲はかわいらしく閉じられます。